
リモートワークが広がりを見せる中、自宅のデスクで仕事をする方々も増えているのではないでしょうか。
そんな状況下で、疲れ目を軽減し、勉強や仕事のパフォーマンスを向上させるデスクライトが注目の的となっています。
もちろん、見た目がおしゃれであることも大切ですが、手元に影を作らないデザインや目に優しい光源が特に人気を集めています。
照明一つで、勉強や仕事に対する集中力が高まったり、逆に気が散ってしまったりするなど、さまざまな影響が出ることがあります。
私自身も、日光に合わせて照明の位置を変えるため、古いLEDのスタンド式を使用しているのですが、最近は疲れ目がひどくなって困っていました。
もしかしたら、このデスクライトが原因かもしれないと思い調査してみたところ、やはりその通りでした。
光源の種類や設置方法、電源の仕様によっては、目に悪影響を与えるタイプも存在することが分かりました。
今回はそんな「避けるべきデスクライト」について詳しくお話ししたいと思います。
目に優しいデスクライトを選ぶためのポイントは3つ

① 光源は3種類
デスクライトで使用される光源は、LED、蛍光灯、白熱電球のいずれかになります。
それぞれのライトの種類によって、光の特性や電力消費量、購入時の価格が大きく異なります。
最近では、省エネ性能が高いLEDタイプが主流となってきています。
最も人気があるのは「LED」
LEDといえば、今やデスクライトの代表とも言える安定した人気を誇っています。
形状や明るさのバリエーションが豊富で、他の光源と比較しても、長寿命で省エネ性が高く、さらに高機能なものでは調光や調色が可能です。
蛍光灯や白熱電球に比べると購入時の価格は高めですが、ランニングコストの低さと長寿命でその分を補っています。
問題点は、「多重影」と「調光ノイズ」
・目に見える問題=「多重影」をご存じですか?
LEDのデスクライトは、小さい光源が集まって、ひとつの明かりに見える仕組みになっています。
つまり、影は光源の数だけ生まれるため、光源の集合体が影の集合体を生じることになります。
多重影が発生すると、動く影に気を取られて集中力が低下し、影との明暗の差が疲れ目を引き起こす原因となります。
これを回避するためには、点発光ではなく面発光を選ぶ必要があります。
LEDタイプを選ぶ際には、多重影対策が施された製品を選ぶことが大切です。
・音が気になる問題=「調光ノイズ」が周囲の機器に影響を与える
これは、LEDの電源部から発生する磁力が周囲の機器に影響を及ぼし、ノイズが生じる現象です。
相性の問題ですが、ライトを点灯させた際にノイズが発生する場合、機器から1メートル以上の距離を置くことで改善されることが多いです。
目に優しい「蛍光灯」
LEDが普及する前は、蛍光灯が主流でした。
蛍光灯は全体から光を放つ「面発光」のため、ムラがなく、自然に近い色調が特徴です。
デメリットは、「非省エネで発熱」と「光の調節ができない」
このようなデメリットとして、LEDに比べて電力を消費し熱を発生させることや、調光機能がない点があります。
それは、「NASA」が開発した「フルスペクトルランプ」を搭載した「ジェントライト」です。
過去にLED化の流れから、一旦販売中止になりましたが、多くの再販希望から復活した蛍光灯デスクライトです。
価格は高めですが、自然光に極めて近く、長時間見ていても目が疲れにくいと言われているほどの目に優しい照明です。
おしゃれなデザインが多い「白熱電球」
インテリアとしての意味合いが強いデスクライトです。
シェード(傘)のデザインが豊富で、実用性よりもデザイン性を重視する方におすすめです。
② 電源は3種類 おすすめはUSB給電
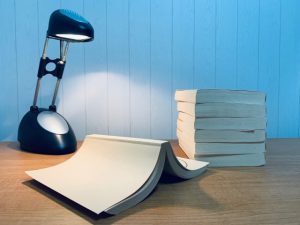
デスクライトは一般的にコンセントに接続されるというイメージが強いですが、電源も進化しています。
設置場所に制限が出るAC式(コンセント式)、USB式、電池式の3種類があります。
ポピュラーな「AC式」
最も一般的なコンセントから給電するタイプです。
設置位置は、コードの届く範囲に限られるため、コンセントから遠い場合には延長コードが必要になります。
バリエーションが豊富な「USB式」
省電力なLEDに使われることが多い、USB給電タイプがあります。
USBのコードをつないだまま使用するタイプと、USBで充電する充電池タイプがあります。
アダプターを介してコンセントからも給電可能で、PCやモバイルバッテリーからも給電できるため、設置場所に困ることがありません。
充電池を搭載し、普段はコードから給電する2wayタイプも停電対策に非常におすすめです。
コードレスである「電池式」
初めは懐中電灯の据え置き型程度でしたが、LEDの普及により実用性のある商品が増えてきました。
電池は、乾電池と充電池の2種類があり、乾電池では容量に制限があるため、充電池仕様が増加しています。
特徴としては、他のタイプに比べ軽量で持ち運びが便利な点と、使用時にコードが外せる点があります。
デメリットとしては、電池が切れると交換や充電の手間がかかり、その間は使用できなくなることです。
③ 机の広さとライトの移動により設置場所が決定される
設置方法は、スタンド、クランプ、クリップの3つがあり、机の大きさや設置位置を変更したいかどうかが重要です。
簡単設置の「スタンド式」
スタンド式は固定されていないため、移動が容易で、影に対する微調整も簡単に行えます。
デメリットとしては、土台があるため大きいライトほど、スペースを必要とします。
広い作業スペースを確保できる「クランプ式」
クランプ式は、机の天板をボルトで締め込んで固定する方法です。
机の上を広く使えるため、特定の位置で作業を行うことに適しており、固定強度が高いため大型のライトにも対応可能です。
ただし、簡単に移動ができないため、アームの届く範囲内でしかライトを動かせません。
デメリットとしては、一度設置すると移動に手間がかかる点が挙げられます。
スタンドとクランプの良いとこ取り「クリップ式」
他の設置方式に比べ、安価な商品が多く、その手軽さで人気があります。
机の上だけでなく、寝る時はベッドに移動するなど、気軽に設置位置を変更できるのが特徴です。
「机の上が広く使えて、移動が楽」という点では非常に優れていますが、クリップで挟むため、固定する場所の厚みによって設置できないこともあるため、注意が必要です。
デメリットとして、固定強度があまり強くなく、大型のライトには不向きです。
目に優しくないのは、ライトが原因かもしれません

蛍光灯が主流だった時代から今日に至るまで、デスクライトの影響によって、目に負担がかかり、疲れ目や眼精疲労を引き起こすケースが多く見られます。
さらに、目を酷使することで視力の低下や頭痛、吐き気に悩まされることがある環境でもあります。
目に優しいデスクライトを選んだつもりが、逆に目に負担をかけることにならないように、4つの要因に注意が必要です。
デスクライトで発生する4つの作用
デスクライトは、最も近い照明として知られています。
近い位置にあるため、影響も出やすく、まぶしさやちらつき、LED特有の多重影、そしてブルーライトの4つが原因として挙げられています。
まぶしさ(グレア)は不快感の元
直接、ライト部分が視界に入ることで、不快感やストレス、まれに目の痛みを引き起こすことがあります。
まぶしさの原因は、光の明るさの違いとその角度です。
1つ目は、光の当たる部分と影の部分の明るさに差が大きいと発生しやすくなります。
2つ目は、身体の状態も関係しています。特に白内障を抱える方は、まぶしさを感じやすい傾向があります。
主流のLEDにはまぶしさが生じやすいことが知られており、対策を講じていないデスクライトは特にまぶしく感じます。
ちらつき(フリッカー)は目の負担を大きくする
LEDに多い「点灯方式」が原因で、ちらつきは発生しやすく、目にかなりの負担をかけてしまうことになります。
「点灯方式」とは、目に見えない短い時間の点滅を繰り返して光る仕組みのことです。
確かに、電力消費が少なく、寿命も長くなる発光方式ですが、それが頭痛や視覚障害の原因になることもあります。
2012年の法改正により、ちらつきを防ぐLEDライトが増えてきていますが、購入時には要チェックです。
多重影は疲れ目を引き起こす
LEDの問題点としても挙げられましたが、小さな光の集合体であるLEDライトは「多重影」を生じやすいです。
現在では、照射方法や向きを工夫して「多重影対策」を施したデスクライトも増えているため、購入時には対策商品を選ぶことが重要です。
ブルーライトは目の奥まで到達する
光は波長が短くなるほど、エネルギーが高くなります。
ブルーライトは可視光の中で最も波長が短く、エネルギーも強いため、網膜まで届いてしまうのです。
また、ブルーライトの散乱性を含めて、目だけでなく体調にも影響を及ぼすことが分かってきています。
最近では、ブルーライト対策が施されたデスクライトも多く出回っているため、購入時にはぜひ確認しましょう。

「疲れ目」と「眼精疲労」の違いを理解していますか?一番の違いは、目に起こる症状の程度です。
「疲れ目」は一時的な疲労で、休息を与えれば回復するレベルです。
一方で、「眼精疲労」は目の疲れだけでなく、頭痛や肩こりなどの不調が繰り返されることになります。
こうした症状を防ぐためにも、デスクライトは慎重に選ぶ必要があります。
まとめ
幼少期から多用され、目に近い位置にあるため、その影響も大きいのがデスクライトです。
集中するためには、白っぽく青みがかったさわやかな昼光色が適しています。
選ぶ際には、目に負担をかけない明るさの目安として「400lm」と「500lx」を推奨します。
「lm」はルーメン、「lx」はルクスと呼ばれ、光の総量および照らされている面の明るさを示します。
結論として、避けるべきデスクライトは「何の対策も取られていない製品」となります。
逆に言えば、「均一でちょうど良い明るさで、影のできにくい位置から照らせるデスクライト」が理想と言えるでしょう。
そのため、私は現在と同じLEDのスタンド式で、目に優しいと評判の「イルミナス」を選ぶことにしました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも目に優しいデスクライトを選んで、大切な目をいたわってあげてくださいね。


